かたがみスタイル用語集
初心者の方は一度軽く目を通しておくと次にチェックしやすいと思います。気がついた部位や名称などを随時増やしていきます
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち と な に ぬ の は ふ
| 【あ】 | |
| あいじるし | ノッチとも言います。布を縫い合わせるときにズレを防いだり、イセやギャザーを入れる位置、縫い代の幅などを示す縫合上の目標となるしるしのこと。マリブでは30cm以上の長さを基準にしてます。縫いの目印をして必要な部分に"1本線"を入れています。合い印部分には切り込みをいれるかチャコペンで色をつけるかしてください。 |
| アームホール(AH) | 袖ぐり、袖ぐり寸法 |
| あきどまり | あきの止まり位置のこと |
| あきみせ | みせかけのあきのこと。見せかけてはいるものの実際はあかない装飾的なあき。ジャケットやコートの袖口に作られることが多いです |
| あらだち | 余分な縫い代を付けて裁断することマリブではパターンにすでに縫い代が含まれています。荒断ちが必要な場合は仕様書でご提案させて頂きます。 |
| 【い】 | |
| いせ | 平面の布を立体的に形づくるための技法。イセる部分を細かくぐし縫いをして糸を軽く引き締めアイロンで立体を形づくる。 下記のような記号で表わされています 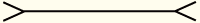 |
| いせこみ | いせ |
| 糸ループ | 釦かけ、カギホックかけ、ベルト通し、スカートやコートの表布と裏布の裾を止める場合に用いる方法。一般的には縫い糸を鎖編みにしてループを作る。 |
| 【う】 | |
| ウエストライン | 腹囲(お腹まわりの)線のこと。洋服を作る上で、また採寸においても最も重要な基準となる線。女性の場合、人体を前面から見てもっともくびれたところを1周した線。 |
| 浮き | ポケット口やフラップがボディーから離れて浮いた感じに形づくられてる場合、その浮いた感じを浮きという。又ベルトループを作る時、平面の状態に浮きを(たるみ)をもたせておきます。それはベルトの厚み分と考えます。 |
| うしろ身頃 | 洋服では主に上半身を覆う部分を身頃といい、肩縫い目あるいは肩線から後ろを後ろ身頃という。(注:パンツ・スカートなどのボトムの後ろ側も後ろ身頃という場合があります) |
| 【え】 | |
| 衿ぐり | 衣服の前後身頃の首付け根位置や衿が身頃に付く位置のこと。衿なしの場合は様々な形のくりがある。ネックラインともいいます。 |
| 衿先 | 衿の角のとがっている部分をさす。 |
| 【お】 | |
| 落としミシン | 縫い目を割り、その割れ目に表からかけるミシン・ステッチ。また、玉縁にしたときのきわにかけるミシン・ステッチのこと。 |
| 【か】 | |
| 返し縫い | ミシン縫いの場合、縫い目の上をもう一度返して縫うこと。手縫いの場合は縫い進めながらひと針前に戻ってすくうことを繰り返すこと。 |
| 肩線 | 首の付け根と肩先を結ぶ線のこと。 |
| カット&ソー | カットソーともいい、ニット素材を裁断、縫製してつくる衣類のアイテムや素材をいう。Tシャツ、トレーナー、ポロシャツ、下着などに多く使用され、スエットともいう。 |
| 仮縫い | 洋服を仕立てる工程の一つで、本縫いの前に出来上がりと同じようにしつけをかけたものを試着し、体型にあわないところやデザイン上の修正などをおこなうこと。 |
| 【き】 | |
| 着丈 | 衣類の後ろ衿ぐりまたは後ろ中心上端から裾までの長さ。 |
| 切り替え | デザイン効果をねらったヨークやパネルライン、プリンセスラインなど。また、体型にあわせるために構造上必要な縫い目のこと。 |
| 【く】 | |
| くせ取り | 平らな布をスチームとアイロンの操作でイセたり、伸ばしたりしながらボディーラインに沿った立体的な形をつくること。 |
| 口布 | 切り込みを入れて作るポケットのポケット口に付けるぬののこと。 |
| 【け】 | |
| 蹴回し | 裾まわりの寸法のこと。 |
| 剣ボロ | シャツやブルゾンなどの袖口の上手口の短冊あきのことで、明き止まりを三角にしたものを言う。メンズのYシャツの袖口に良く見る。もちろんレディースでも使用するデザインです。 |
| 【こ】 | |
| コバステッチ | 布の折り端の飾り縫いのこと。折り端、または縫い目端の1〜2?程度のところにかけるステッチ。 |
| 【さ】 | |
| 差し込み | 生地を裁断するときに布の無駄をなくすため、型紙を上下関係なく互い違いに入れ込むこと。但し布目は正しくあわせる。無地。細かい柄、毛並みのない布に用いる方法。 |
| 【し】 | |
| しつけ | 本縫いをする前に仮にとじておくこと。縫い目や折り目を正確に、また縫いやすくするために固定しておく押さえ縫いのことを言う。 |
| 地直し | 裁断する前に形くずれや寸法のくるいを防ぐため、布を整えること。天然繊維の織物は湿気にあたると縮みやすいので、スチームを当てたり、水に浸けて収縮させ、 さらにアイロンをかける。 |
| 地の目 | 布地の経(たて)糸、緯(よこ)糸の織り目のこと。布目ともいう。衣服を製作するうえで布目を正しく扱うことは服の形くずれを防ぐもっとも大切な条件になる。 |
| 【す】 | |
| 裾上げ | 衣服の下のヘリの折り代を出来上がり線で折り、まつったりかがったり、ミシンをかけたりして始末すること。 |
| 捨てミシン | 裁ち目の始末のひとつで裁ち端のほつれ防止にかけるミシンのこと。 |
| ステッチ | 針目、縫い目のこと。表から見える縫い目で、飾り縫いをする時に使われることが多い。 |
| スナップあき | スナップで留められた明きのこと。取り付け方法、開閉操作が簡単な上に軽くソフトに仕上げられるのが特徴。 |
| 頭回り | 眉間から耳の上部を通り後頭部の突出部を通る周囲の長さ。かぶる衣服の衿あき寸法を決める時や帽子などを作るときに必要な寸法。 |
| 【せ】 | |
| 正バイアス | バイアスとは斜めに裁つことで正バイアスは45度の角度で正しく斜めに裁つことを言う。一般的にバイアスと呼ぶ。45度以下の場合は「ちょこっとバイアス」と呼んでいます。 |
| センターフロント(CF) | 前中心のこと。 |
| センターバック(CB) | 後中心のこと。 |
| 【そ】 | |
| 袖付け | 袖を身頃に縫い合わせること。または身頃側の縫いつけ位置を言う。 |
| 袖山 | 袖のカーブの頂点。合印を必ず入れるポイントになる個所。ここは合印と記さずに袖山の記す。 |
| 外表 | 2枚の布を重ねて裁断したり縫い合わせたりする時、両方の布の表面が外側になるように重ね合わせることを言う。反対は中表(なかおもて)と言う。 |
| 【た】 | |
| 裁ち | 布などを裁断すること。 |
| ダーツ | 平面的な布を立体的にする技法の一つ。人体の凸凹に合わせて丸みやふくらみを出すために、布の一部をつまんで縫い消すつまみのこと。 |
| 玉止め | 手縫いの縫い終わりの止めのこと。縫い始めの玉結びに対して玉止めと言う。 |
| 玉結び | 糸の結び方の一つ。縫い始める前に糸端に結び玉をつくること。 |
| 【ち】 | |
| 千鳥掛け | 糸を斜めに交差させ上下交互に返し針を繰り返し刺したもの。 |
| 力芯地 | 裏芯。ホールボタンやポケットの口など力がかかる部分の裏に貼るシンジ。 |
| 力布め | ボタンやポケットの裏にする補強布のこと。 |
| 着分 | 服一着が作れる長さにしてある布。「一着分」の略 |
| 【と】 | |
| 綴じ | 中とじなどのこと。表と裏の衿つけの縫い代を止めたり、脇などの表布と裏布を止めるときに、粗い針目でとじ合わせること。 |
| 共布 | 色、柄、素材が同じ布のこと。 |
| 【な】 | |
| 中表 | 2枚の布を表が内側になるように重ねること。反対は外表(そとおもて)。 |
| 中綴じ | 裏付きの仕立てで、表の身頃と裏地がズレないように縫い代どうしを粗い針目で縫いとめること。 |
| 【に】 | |
| 二度縫い | 一般に縫い目のミシンは1回を示すが、特に運動量の多い個所、袖付け部分や股ぐり、股下などの縫い目は着用時に力がかかるので縫い糸が切れたりしないように同一線上を2度ミシンをかけること。 |
| 【ぬ】 | |
| 布目 | 地の目のこと。 |
| 【の】 | |
| 伸び止め | 縫い目が伸びるのを防ぐこと。テープなどを貼ったり捨てミシンをかけて、伸びを防ぐ作業のこと。 |
| 【は】 | |
| バイアス | 斜め方向に裁断したり、斜めに裁断した布のこと。 |
| 接ぐ(はぐ) | 接ぎ、つぐ、つぎとも言い、縫い合わせること。 |
| 端ミシン | 布の端から1〜3mmのところを本縫いすること。 参考図:二つ折端ミシン 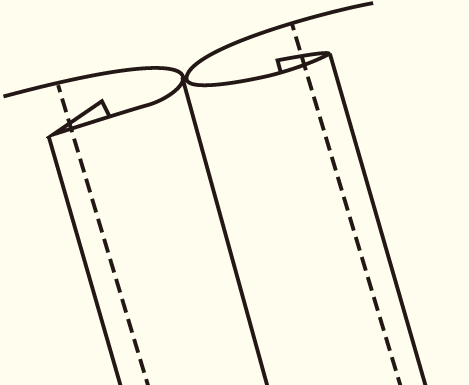 |
| 針目 | 一般的にある間の縫い目の数の規格をいう。日本では地縫いの場合、3cm間に10〜12針を基準としている。3cm間に12針は12針/3cmと記す。 |
| 【ふ】 | |
| ふき(ふき代) | 衿や袖口でわざと裏地を見せたり、逆に表衿を裏衿より少しだけ出したりするすること。 |
| 袋縫い | 二枚の布を外側に合わせて縫ったあとに裏に返して裁ち目を中に包むように縫い合わせること。 |
| 袋布 | 接ポケットの内側の袋になる部分のこと。 |
| 布帛(ふはく) | 棉、麻、絹、(またはそれらを混合したもの)を原糸とする織物の総称。 |
| 部分縫い | ポケットやカフス、衿などの縫製方法を理解するために一部分を縫ってみること。 |